茶道具の楽しみ(茶があるということ) 2000年1月 9日 01:00 投稿
池田 瓢阿 昭和60年6月27日
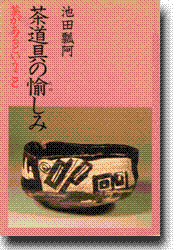 この著書は、是非、あとがきから読んで欲しい。そういった方法はイレギュラーかもしれんないが、そうした後、各章を読みすすめていくと一層面白くなると思う。読後、あとがきを読みながらの後悔の言葉である。
この著書は、是非、あとがきから読んで欲しい。そういった方法はイレギュラーかもしれんないが、そうした後、各章を読みすすめていくと一層面白くなると思う。読後、あとがきを読みながらの後悔の言葉である。
では、本題に入ろう。なぜ、茶道をしているのか問われることがある。「花嫁修行」だと思う人は先ずいないだろう。ま、それに通じるところの「行儀作法」でも身につけようとしているのか、それとも着物を着てみたいのか、等々、他人がどう思っているのかを想像してみるのも、また楽しいものである。想像という言葉で思い出したのだが、茶道というものは実は非常に想像力を必要としているものではないか、というのが最近の私の思うところでもある。
さて、池田瓢阿氏の著書はこれで2冊目になる。前回は、ある茶人が還暦の茶会を催すまでの悪戦苦闘の日々を日記風にまとめたものだった。今回の「茶道具の楽しみは」一話完結の随筆集という形にまとめられている。サラッと読めてしまうのは、気が楽な反面、もうちょっと突っ込んで書き込んで欲しいなと思うところもあり(ページの制約上致し方ないのだろう)、そういった部分は今後の自身の課題ということで勉強していこうと考えている。完璧なものを好まない傾向がある茶道という世界では、もの足りなさのある書き方も「茶がある」ということに繋がっていくとすれば、これもまた、想像力を働かせる良い機会となるようだ。
副題の(茶があるということ)を根っこに持たせながらの話の展開は、実に心憎くもあるのだが、茶を知らない人にとっては、こんなにつまらない読み物もないのではないかと推察する。前述したように「つっこみ」が少ないために、茶を知らない素人には『茶道はつまらない』と思われても致し方ないだろう。こういった読み物は、その道を知っている・理解している人のためには有用だが、素人には無益な読み物になってしまうようだ。もっとも、著者自身も対象となる読者を限定して書いているのだから、こういった話の展開を批判する気は毛頭無い。私は十二分に楽しんだのだから、それも(茶がある)という読書の方法かもしれない。
竹芸家の瓢阿氏にとって「茶道」は仕事の為に収得したといってもいいと思う。ですから、時間があれば窯を尋ねて「作陶」をし、また和漢朗詠集等の文字を手習いし、そして骨董屋巡りと、時間と唯物的な余裕があれば私も。。。うらやましくなるような生き方をされている。それなりの苦労はあると推察するところだが(茶道具を作る人なのだから、茶道に精通していることは、先ず、第一条件だろう)、こういった書物を読んでしまうと、茶道とは俗世を離れた所に鎮座しているようにも感じてしまう。
「茶道は知的遊戯である」と著者も言い切っているが(私もこの考えには同感である)、そういった楽しみを庶民の位置に引きずりおろす方法を期待してしまう。茶がある生活を庶民にも味わって欲しいというのが、私の今後の課題でもあるようだ。この答えの一部はあとがきに記述されていたのだが、その回答を知りながら読むと、茶道を知らない人にも面白く読める本だと思う。
発行元 主婦の友社