初釜と茶事 1998年1月11日 00:00 投稿
本来は新年を祝って最初に掛ける釜を「初釜」というそうです。ですから私達の社中の場合は「初寄り」といったほうが良いかもしれません。
今年の初釜も昨年同様に、駒込にある女子栄養大学構内の「松柏軒」で茶懐石をいただきながらの初釜になりました。茶道の日頃の稽古は「茶事」(ちゃじと読みます)の為にありますので、この日の初釜は省略されている部分はあると言っても、かなり本格的な「茶事」に近いものです。このように正午ごろから始めるお茶事を「正午の茶事」と言います。茶事には他にこの正午の茶事を基本にして七式ありますが、これについては手習い帳に簡単に記してありますので、参考にしてください。
社中ではまだ若いほう、おまけに4年の新米ですので、準備をするのは毎年のことですが、この準備のおかげで茶道の基本をだいぶ勉強させていただきました。まずは掃除。必ず、雑巾掛けをします。次にお道具の用意をして洗う。次は茶を掃き、茶入れや茶器に入れ、水差しの用意や棚を置いたりと、本当にやることはたくさんあります。客のもてなしはここから始まりますので、水屋仕事は全ての基本だと思って、進んでやらせていただいています。
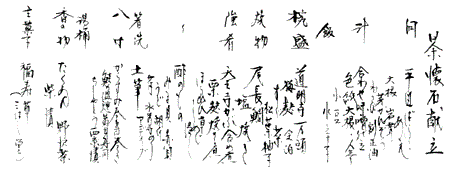
主 香 湯 八 箸 強 焼 椀 飯 汁 向 菓 の 桶 寸 洗 肴 き 盛 子 物 物 福 た か 土 酢 栗 天 尾 道 合 平 寿 く ち 鮭 ら 筆 み の ほ 麸 王 張 梅 明 色 わ 大 目 草 あ し の す る 物 う 焼 寺 鯛 麸 寺 紙 せ 根 ば ん ゃ 温 み ア 貝 れ き か 塩 万 大 味 ら と 燻 の ン ん 煮 ぶ 焼 金 頭 根 噌 岩 こ 野 う 黄 奉 デ 赤 草 含 き 箔 仕 茸 あ 沢 西 身 書 ィ 貝 め 人 立 え 菜 京 寿 巻 ブ し 煮 す 参 芽 漬 司 き う め ず か 柴 ど じ 菜 小 ん 漬 浸 豆 ぞ け 胡 し 松 う 瓜 葉 水 柚 辛 わ 芋 子 子 さ び 水 前 割 寺 醤 の 油 り
これは洋食のフルコースのようなものですが、味はいたって淡泊で、見た目や香りをとても大切にしているところは、食に対する人間の感覚は、洋の東西を問わず同じようなものなのでしょう。茶懐石のいただき方や料理についてもついても、折りをみてお話したいと思っていますが、まだまだ勉強が足りません。自分で作れるようになるのが、夢ではありますが、どこかに修行にいかないと、こればかりは無理なような気がします。やっぱりプロが作ったものはおいしいかったです。